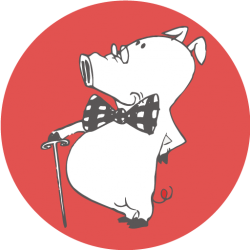◎後援依頼という新しい試み
今回自身の新たな試みとして、この絵本の原画制作に欠かせない画材のメーカー様三社に名義後援のお願いをしてみた。今回打診をする前から、有り難いことにご縁があり、無名の私の申し出でも、快く快諾を頂いた。個人の展覧会に企業の後援って頂けるのだろうか?とドキドキしながらのお願いであったが、本当に有り難いこだと思う。この場を借りて厚く御礼申し上げます。
◎欠かせない三つの画材とは?
今回お願いをした画材メーカー様は下記の通り。
- 特種東海製紙株式会社様製 いづみN紙
- 株式会社中里様製 極品隈取筆
- ホルベイン画材株式会社様 アーチスト・パンカラー
※上記の各製品名は、それぞれの製品紹介ページにリンクしています。
※以下の文中の会社名は敬称略で記します。
・いづみN紙

この原画は、付けペンとインクで輪郭線を、彩色は主に透明水彩絵の具で塗っている。(ごく一部に不透明水彩やアクリルカラーインクなども使用している。)経験のある方はご存知だろうが、ペンの引っかかりが少ない紙(ケント紙など)は、逆に水彩絵の具がのりにくい。反対に水彩絵の具の塗りやすい紙(マーメイド紙やキャンソン紙など)は、表面がザラザラとしているため、ペンで線をひくと紙に引っ掛かってしまい、線が描きにくい。以前、大学の恩師が作品でイタリア・ファブリアーノ社製の版画用紙を使ってられたのだが、これはペンも水彩も良い感じに使えるのは知っていた。しかしこの紙の弱点は、消しゴムをかけるとすぐに毛羽立ってしまうことだ。今回の絵は、恐らく清書の段階でも訂正が入ったりする可能性が高いと考えると、すぐに毛羽立ってしまう紙は使えない。大学在学時に良い紙はないか?と探していて、学内の購買部(画箋堂さん:京都では有名な画材屋さん。河原町五条にあります。)で色んな紙を試していたときに見つけたのが、ファブリアーノと同じ版画用の紙で日本製のいづみN紙だった。これは付けペン、透明水彩、消しゴム、すべてOKの、私にとってみれば願ってもない紙だった。(当時のカートゥーン作品制作では、好んでこの紙を使っていた。)
・極品隈取筆

大学在学時から、大学の恩師の紹介でイベントなどでの似顔絵執筆を始めた。かれこれキャリアは30年以上となる訳だが、恩師の最初の教えやご一緒させて頂いた諸先輩方の画材の影響か、最初から色紙に和筆と墨、絵の具という形のまま今日まで来た。イベント席描きの似顔絵=色紙が一般的だったので、色紙に合う画材ということで自然にそうなった。
そこで、彩色に関して最初は(当然というか)彩色筆を使っていた訳だが、程なく隈取筆と出会った。髙島屋京都店でのイベントで隈取筆を使って描いていたら、髙島屋の宣伝部の社員で京都市立芸大の日本画を出られた方に、「隈取をそこまで使いこなすなんてたいしたもんだ」と言って頂けたのは嬉しい想い出だ。隈取筆というのは、売り場の説明書きに「ぼかしに使われる」と書かれてあっても、本来の使い方を正式に教わる機会のないまま、自分流に使い続けて30年余りが過ぎてしまった。今回のトークSHOW開催にあたり、ネットで本来の使い方を調べてみた。結果、普通に水彩をぼかすときに塗る塗り方だった。濃いめに水で溶いた絵の具をたっぷりと紙に置き、水だけを含ませた隈取筆で撫でるようにすると、溜まった絵の具と筆の水が溶け合わさって薄くぼかす、というものだ。
しかし私の隈取を使ったぼかしは、一般的なぼかし方とは全く違う。似顔絵の席描きで培った筆使いから出て来たクロスハッチング風ぼかしである。ここ最近、和筆で線を描くのは、鳩居堂の即妙筆がお気に入りだ。これは一番大きい直径の筆ですら、髪の毛位細い線がひける。太いのから細いのまで自在に描ける凄い筆だ。なので、当初は鳩居堂で隈取筆も買っていた。個人的に思う鳩居堂の筆の特徴は、命毛(筆の真ん中にあるハリのある一本の毛)の長さである。即妙はその命毛だけで描くことで細い線がひける。隈取筆も命毛がピンと出ていて、そこに周りの毛がまとまって描きやすいのだが、隈取筆を平筆のように平らにしたときに、その命毛が邪魔をして平らになりにくいのだ。描きやすい筆ではあるのだが、その点は不満だったので、どこかに自分の描き方にあった筆はないものか…と、近所の画材屋さんで筆を探していた際に出会ったのが、中里の隈取筆だった。中里の隈取筆は平らにした際に本当にフラットになるので広い面積を塗るときにとても塗りやすかった。そして中里の筆を調べていくうちに、「極品」というグレードがあることに気付く。早速購入して使ってみると、「上製」というグレードのものに比べて反応が全く違った。例えるなら、初代のガンダムでマグネット・コーティングする前と後という感じだ。不肖アムロの僕の反応を素早く受け止めてくれるマグネット・コーティング後のガンダムとも言うべき筆が、中里の極品隈取筆なのだ。(却って例えが難解になったかも知れません…)
・アーチスト・パンカラー

大学生の頃に使っていた水彩絵の具といえば、もっぱらホルベインだった。赤い箱に入ったチューブ入りのやつである。大学2年でKBS京都テレビの番組用イラストの仕事を大学の恩師に紹介してもらい、これをホルベインの透明水彩絵の具で塗っていた。
時が経ち、画材の知識も深くなると、透明水彩絵の具も海外のものがあることを知る。ちょうど大学の恩師が、ウィンザー&ニュートンというイギリスの画材メーカーの筆を使い始めた時期だ。このウィンザー&ニュートンというメーカー、英国王室御用達で品質も凄く高い。当然お値段も…。筆なんかはコリンスキーセーブル筆の一番大きいシリーズ7というものが当時1本15,000円位していたと思う。そして透明水彩絵の具も凄かった。頑張って購入して試してみると、水で薄めたときの色の発色の違いに驚かされた。
当時のホルベインのチューブの絵の具の赤を多めの水で薄めてピンクを作るとする。その発色と、ウィンザー&ニュートンの赤い絵の具を薄めて作ったピンクを比べると、輝きが全く違ったのだ。品質は使っている材料に比例するだろうから、一本の単価が全く違う二製品を比べるのは酷というものだとは、今になって思うが、当時の私にとってこの発色のよさという衝撃は凄いものがあった。
そんな経緯でウィンザー&ニュートンの筆と絵の具(チューブと固形の両方揃えてしまった…)を使うという時代が長く続いたが、和筆というものを改めて使ってみて、西洋の筆に比べて値段が安いものでも、西洋の筆以上に質が良いことに気付いた。(ここら辺はまた別の機会にお話しします)。日本製品の質の高さということが方々で聞かれる昨今、自分自身、画材のメーカーも見直してみようというマイブームがあった。席描きの似顔絵の際に、固形水彩絵の具は持ち運びの点でも便利なので好んで使っている。これまでもっぱらドイツのペリカンの固形水彩絵の具をメインに使っていた。これも質は高く、値段もお高い。何故ウィンザー&ニュートンの固形絵の具を使わないかというと、ペリカンの固形絵の具はウィンザー&ニュートンのそれより倍以上の量があるにもかかわらずお値段が同じくらいだったからだ。絵の具一つ一つがそこそこのサイズ感なので、現場での取り回しがとてもしやすい、野外スケッチ向きとでもいえるような安定感がある。
そもそもペリカンを知ったきっかけにも想い出がある。京都市立銅駝美術工芸高校に通っていた時、皆勤賞をもらう機会があった。その賞の記念品としてペリカン固形透明水彩絵の具12色セットをもらったのだ。最初は使いあぐねていたけど、似顔絵の際に便利だと気づいて以来、ペリカンが定番となった。(当時もらったモデルは、絵の具のサイズがウィンザー&ニュートンと同じ位のサイズだったが、その後のリニューアルでお得感溢れる大容量サイズへと進化した。そんな経緯で、似顔絵に行くときはペリカンの固形絵の具を使っていた次第である。
そんな折(10年程前)、京都岡崎にあるみやこめっせで画材フェアが開催されていた。そこに観に行った際にホルベインのブースで見つけたのが、アーチスト・パンカラーだった。これはそれまでのホルベインの固形水彩絵の具と比べ値段が格段に高いもので、これは発色が良いかも!!と思い購入してみた。試してみたら、ウィンザー&ニュートンと同じように、輝くような発色の絵の具だったので、これは凄い!と喜んだ。
◎絵本制作にあたって
今回の仕事の依頼があった際に、手書きで描くということは決めていたので、どういう画材を使って描けば一番効果的なのだろうか?と熟慮した結果、今回揚げた三つの画材を中心に使おうと決めた。すぐに毛羽立たず付けペンも水彩も使える紙と、発色の良い絵の具、自身で編み出したクロスハッチング風ぼかしを可能にする筆、この三つのうち、一つ欠けても今回の絵は成立しなかった。そんな画材に深く感謝しているし、この凄さを少しでも多くの人に伝えたいな、と思い立ったのが、後援をお願いしたきっかけだ。会場には製品紹介のパネルと共にメーカー様のご提供で実物の画材も展示している。またトークSHOWでは、これらの画材をどう使って描いたのか、簡単な実演も交えてお話ししたいと思っている。是非会場で、またトークSHOWで、私の熱い想いに触れて頂ければ幸いです。
たなべたい記
※2025/11/10 訂正
文中で「隈取筆」のことを多数「熊取筆」と表記していました。正しくは「隈取筆」です。ここに訂正すると共に、株式会社中里樣に謹んでお詫び申し上げます。